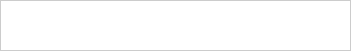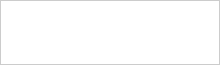五十肩(肩関節周囲炎)、こんなことでお困りではありませんか
五十肩(肩関節周囲炎)の定義
五十肩(肩関節周囲炎)とは、50歳代を中心とした中年以降に発症する肩関節の痛みと運動制限を特徴とする疾患です。正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれ、肩関節を取り囲む関節包や腱板、滑液包などの軟部組織に炎症が起こることで発症します。明らかな外傷がないにも関わらず突然肩の痛みが現れ、腕を上げる動作が困難になり、夜間に痛みが強くなるのが特徴的な症状です。一般的に「四十肩」「五十肩」と年代で呼び分けられますが、医学的には同じ病態を指しています。
この症状に悩む人の推定患者数
厚生労働省の平成19年国民生活基礎調査によると、肩こりは女性では第1位、男性では第2位の自覚症状となっており、肩周囲の症状で悩む人は非常に多いことがわかります。五十肩については、40〜60代の約7割が肩の痛みを経験するとされ、糖尿病患者においては10〜20%が五十肩に悩まされているという調査結果があります。また、五十肩で受診した患者の約3割に糖尿病が発見されるという報告もあり、生活習慣病との関連性も指摘されています。総合的に見ると、日本国内で五十肩に悩む潜在的な患者数は数百万人規模に上ると推定されています。
この症状を放置するとどうなるか
五十肩を放置すると段階的に症状が悪化していきます。急性期の激しい痛みが慢性化し、肩関節の癒着や拘縮が進行して可動域が著しく制限されます。初期には腕を上げる動作のみが困難だったものが、進行すると日常生活の基本動作すべてに支障をきたすようになります。具体的には、衣服の着脱、洗髪、歯磨き、食事動作などが困難になり、QOL(生活の質)が大幅に低下します。さらに放置すると「凍結肩」と呼ばれる状態になり、肩関節が完全に固まって動かなくなる可能性があります。また、痛みをかばうことで反対側の肩や首、腰に負担がかかり、全身の不調や二次的な痛みを引き起こすリスクも高まります。治療開始が遅れるほど回復に時間がかかり、完全な機能回復が困難になる場合もあります。
五十肩(肩関節周囲炎)の一般的な原因について
加齢による肩関節周囲組織の退行性変化
年齢を重ねることで肩関節を構成する関節包、腱板、滑液包などの軟部組織が変性し、柔軟性を失います。これにより炎症が起こりやすくなり、痛みや可動域制限が生じます。
糖尿病などの生活習慣病
糖尿病患者は血糖コントロール不良により血行不良が生じ、肩関節周囲の治癒力が低下します。糖尿病患者の10〜20%が五十肩を発症するという報告があります。
肩関節の使いすぎや微細な損傷の蓄積
長年の肩の酷使により腱板や関節包に微細な損傷が蓄積し、炎症の引き金となります。特に肩を上げる動作を繰り返す職業や運動をしている人に多く見られます。
姿勢不良と肩周囲筋の筋力低下
猫背などの不良姿勢が続くと肩甲骨周囲筋が弱化し、肩関節のバランスが崩れて炎症が起こりやすくなります。現代のデスクワーク中心の生活様式も発症要因となります。
ホルモンバランスの変化
特に女性では更年期のホルモンバランスの変化により、結合組織の代謝が変化し、肩関節周囲炎を発症しやすくなるとされています。
病院での一般的な対処法
薬物療法
非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)の内服薬や外用薬により炎症と痛みを抑制します。痛みが強い場合はステロイド注射や局所麻酔薬の関節内注射も行われます。
運動療法・理学療法
痛みが軽減した慢性期には、肩関節の可動域改善と筋力強化を目的とした運動療法を実施します。振り子運動(コッドマン体操)や段階的なストレッチングが中心となります。
物理療法
温熱療法、超音波療法、電気治療により血行改善と痛みの軽減を図ります。肩を温めることで筋肉の緊張を和らげ、関節の動きを改善します。
生活指導
肩に負担をかける動作の制限、保温指導、睡眠時の姿勢指導など、日常生活での注意点について指導を行います。
関節内注射
ヒアルロン酸やステロイド剤の関節内注射により、直接的な消炎効果と潤滑作用の改善を図ります。
手術療法
保存療法で改善しない場合、関節鏡視下手術による癒着剥離術や関節授動術が検討されます。最近では低侵襲な内視鏡手術も普及しています。
患者さんがよく抱く疑問
・五十肩は自然に治りますか?
・五十肩の人がやってはいけないことは?
・どのくらいの期間で治りますか?
・痛みを我慢して動かした方がいいですか?
・注射治療は効果がありますか?
・温めた方がいいですか、冷やした方がいいですか?
・夜間の痛みを和らげる方法はありますか?
・運動はいつから始めればよいですか?
・手術が必要になることはありますか?
・糖尿病と関係があると聞きましたが本当ですか?
山田治療院からの回答
五十肩は自然に治りますか?
多くの場合、1〜2年で自然回復しますが、適切な治療により回復期間を大幅に短縮できます。当院では神経系の働きを整えることで、より早期の回復を実現しています。
五十肩の人がやってはいけないことは?
痛みを我慢して無理に動かすことは避けるべきです。ただし完全な安静も拘縮を進行させるため、適切な範囲での動きを維持することが重要です。
どのくらいの期間で治りますか?
症状の程度により異なりますが、当院での神経系アプローチにより、多くの方が3〜6ヶ月で大幅な改善を実感されます。従来の治療より早期回復が期待できます。
痛みを我慢して動かした方がいいですか?
痛みは身体からの重要なサインです。強い痛みを我慢するのではなく、神経系の働きを正常化することで、自然に動きが改善していくアプローチを行います。
注射治療は効果がありますか?
注射は一時的な症状緩和には効果的ですが、根本的な解決にはなりません。当院では注射に頼らず、身体の自然な治癒力を高める治療を行っています。
温めた方がいいですか、冷やした方がいいですか?
一般的には温めることが推奨されますが、神経系の状態を整えることで、身体が自然に適切な血流調整を行えるようになります。
夜間の痛みを和らげる方法はありますか?
夜間痛は神経系の過敏状態が原因です。神経系の働きを正常化することで、夜間の痛みも大幅に軽減されます。睡眠の質も向上します。
運動はいつから始めればよいですか?
従来の段階的運動ではなく、神経系の協調性を高める動きから始めます。痛みの状態に関わらず、適切な身体の使い方を身につけることが可能です。
手術が必要になることはありますか?
当院の治療により、多くの方が手術を回避されています。神経系へのアプローチにより、癒着や拘縮の改善も期待できます。
糖尿病と関係があると聞きましたが本当ですか?
糖尿病と五十肩には関連性がありますが、神経系の働きを整えることで、糖尿病の有無に関わらず症状の改善が期待できます。
どんな流れで治療を行うの?
1.治療に入る前、問診を行います。
まずは手技療法で治る範囲の症状であるかどうかを、確認します。
特に、施術によってかえって悪化する可能性が高かったり、緊急で病院での処置が必要な症状であったりする場合は、この時点で施術を中止にいたします。
2.施術台に移動し、触診と各種検査を行います。
症状の原因であろう箇所や、問題がある箇所を検査によってあぶりだしていきます。
筋肉、内臓、神経、血管などの状態を確認していきます。
3.見立ての検証を行います。
原因と思われる箇所に刺激をすることで症状が軽減するかどうかを調べます。
軽度の症状ですと、この時点でもほぼ治ってしまうこともあります。
4.施術いたします。
全身の状態を確認しながら、原因箇所を緊張させている要因を外していきます。
この際に、症状や状態にあわせて、さまざまな治療法を用います。
5.主訴の軽減・解消の確認をいたします。
術後、体を動かして具合を確認していただきます。
必要に応じて、さらにいくつかの手技を行う場合もあります。
6.その場でできることが終わったら、その状態にあわせてセルフケア法をお伝えします。

五十肩(肩関節周囲炎)についての情報の引用元
・東北大学整形外科学教室「わかりやすい五十肩・肩の痛み」
・メディカルノート「肩関節周囲炎(五十肩)―日常生活の注意点と予防」
・厚生労働省「令和5年患者調査傷病分類編(傷病別年次推移表)」
・糖尿病ネットワーク「『五十肩』は糖尿病の人がなりやすい 肩の痛みにこうして対策」
・日本理学療法士協会「肩関節周囲炎 肩にやさしい関わり方で快適な生活を」
・各種医療機関の五十肩治療に関する専門情報
・整形外科専門医による肩関節周囲炎の診断・治療に関する文献
・厚生労働省「平成19年国民生活基礎調査」